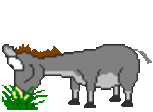雑学・和歌山→記事一覧 投稿した記事が増えてきましたので目次と要約のサイトにリンクしました(2010.4.3)。画像も増えてきましたので、雑学・和歌山 MY ALBUMにリンクしました(2011.2.12)。
2010年09月15日
和歌山市の景観行政(計画)
景観法が平成16年12月に制定されてから、6年目を迎えようとしています。
その6年目の今年。
和歌山市は景観計画と条例の制定作業に着手しました。まさに和歌山市にとって景観元年にあたると言えます。
ぶちゃっげて言うと、和歌山市は平成22年5月になって、ようやく景観計画・景観条例等制定の検討を始めたのです。すでに和歌山県は、和歌山県景観計画を定め、平成21年1月1日より施行しています。
高野山町も平成20年1月1日付けで『景観行政団体』になり、翌平成21年3月9日から景観計画をスタートさせています。 高野町は、和歌山県知事の同意を得て景観行政団体になることにより、独自の地域性を活かした景観づくり(景観法に基づいた景観条例の策定、景観計画の策定)を行うこととしたのです。このことは立派な行政姿勢だと思います。
景観法では、政令都市、中核市、都道府県は、自動的に景観行政団体となります。和歌山市は中核市であるので、自動的に景観行政団体となります。
それではちょっと気になるところを記しておくこととします。
①タイトル
和歌山市景観計画となるのだろうか。それとも、風景或いは風土計画となるのだろうか。それとももっと平たく「和歌山市を磨く景観計画」?
景観とは、通常眼に見えるものを指しますが、風景とは眼に見えない(風)ものも含んでいます。例えば心象風景など。障害者をも含めた計画作りを目指すためにも一考すべきことかもしれません。一部先進自治体では、風景計画という言葉を使っています。
②和歌山市の景観の現状把握
県の計画では、県の景観の現状についての記述はわずか3~4行ぐらい。以下のとおりです。
「和歌山県の景観は、緑なす紀伊山地の山々、変化に富んだ海岸地形、河川の流域ごと
の文化圏のまとまりなどによりその骨格が形成されている。和歌山県では山岳信仰を育
んできた雄大な山地、朝陽や夕陽に映える海岸部、そして河川の流域ごとの地域文化を
反映した集落や市街地などその美しい景観が保たれている。」
これでは簡単すぎます。ある自治体の景観計画では、自治体の現状について各地域ごとに類型化して分析しています。驚くことに当該市にある樹木数まで55万5千本などと数えているのです。
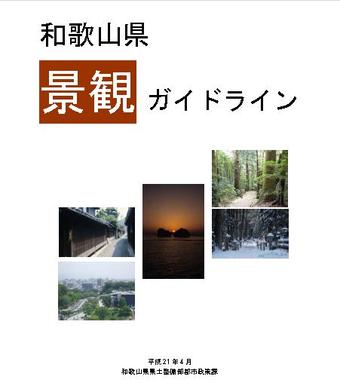
もちろん、そこまでする必要はないと思います。でも、市内にある公園数・面積(4次長期計画で調査済み)、モニュメント(わたしが知っているのは、大田左近、雑賀孫一、南方熊楠、紀州犬、虎伏像、陸奥宗光ぐらい)、重要樹木、重要建築物、寺院、神社、お地蔵さま、指定名所、文化財、名水、その他沿道から観た景観などを地域類型ごとに纏めることができるなら素晴らしい。それらデータを見ることによりその地域の景観の現状の詳細がわかり、今後の方向を議論する基本データになりうる。
③計画期間
景観計画は、子供を育てるような長い時間が必要であると言われています。多くの先行計画では目標年次を定めていないようです。しかし、計画は何時までと書かなくては、計画ではありません。例えば、当面国体開催年度の2015年までとするのも一案だと思います。
④市民の参画
この仕組みづくりこそ、実は一等大事なことのひとつであると思っています。例えば、景観市民会議を設置して、毎年特定地点からのレビューを市民メンバーに評価してもらう。そして提案をしてもらう。
良き景観を守り、形成していくことは、地元自治体が如何に市民の景観意識を向上させる仕組みを作るか、の一点に懸かっています。そのための景観計画の策定だと思います。
そして、これを実現するのはやはり人材です。この計画は息の長い計画であるが、行政と住民等が一歩一歩より良き地域づくりを作っていくための強力なツールになって欲しいと願っています。
和歌山県景観ガイドライン
その6年目の今年。
和歌山市は景観計画と条例の制定作業に着手しました。まさに和歌山市にとって景観元年にあたると言えます。
ぶちゃっげて言うと、和歌山市は平成22年5月になって、ようやく景観計画・景観条例等制定の検討を始めたのです。すでに和歌山県は、和歌山県景観計画を定め、平成21年1月1日より施行しています。
高野山町も平成20年1月1日付けで『景観行政団体』になり、翌平成21年3月9日から景観計画をスタートさせています。 高野町は、和歌山県知事の同意を得て景観行政団体になることにより、独自の地域性を活かした景観づくり(景観法に基づいた景観条例の策定、景観計画の策定)を行うこととしたのです。このことは立派な行政姿勢だと思います。
景観法では、政令都市、中核市、都道府県は、自動的に景観行政団体となります。和歌山市は中核市であるので、自動的に景観行政団体となります。
それではちょっと気になるところを記しておくこととします。
①タイトル
和歌山市景観計画となるのだろうか。それとも、風景或いは風土計画となるのだろうか。それとももっと平たく「和歌山市を磨く景観計画」?
景観とは、通常眼に見えるものを指しますが、風景とは眼に見えない(風)ものも含んでいます。例えば心象風景など。障害者をも含めた計画作りを目指すためにも一考すべきことかもしれません。一部先進自治体では、風景計画という言葉を使っています。
②和歌山市の景観の現状把握
県の計画では、県の景観の現状についての記述はわずか3~4行ぐらい。以下のとおりです。
「和歌山県の景観は、緑なす紀伊山地の山々、変化に富んだ海岸地形、河川の流域ごと
の文化圏のまとまりなどによりその骨格が形成されている。和歌山県では山岳信仰を育
んできた雄大な山地、朝陽や夕陽に映える海岸部、そして河川の流域ごとの地域文化を
反映した集落や市街地などその美しい景観が保たれている。」
これでは簡単すぎます。ある自治体の景観計画では、自治体の現状について各地域ごとに類型化して分析しています。驚くことに当該市にある樹木数まで55万5千本などと数えているのです。
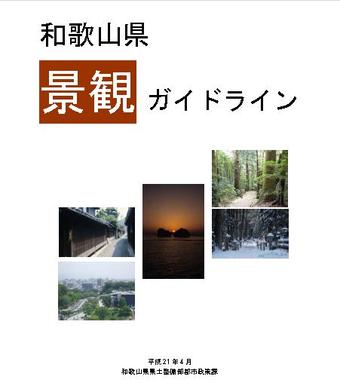
もちろん、そこまでする必要はないと思います。でも、市内にある公園数・面積(4次長期計画で調査済み)、モニュメント(わたしが知っているのは、大田左近、雑賀孫一、南方熊楠、紀州犬、虎伏像、陸奥宗光ぐらい)、重要樹木、重要建築物、寺院、神社、お地蔵さま、指定名所、文化財、名水、その他沿道から観た景観などを地域類型ごとに纏めることができるなら素晴らしい。それらデータを見ることによりその地域の景観の現状の詳細がわかり、今後の方向を議論する基本データになりうる。
③計画期間
景観計画は、子供を育てるような長い時間が必要であると言われています。多くの先行計画では目標年次を定めていないようです。しかし、計画は何時までと書かなくては、計画ではありません。例えば、当面国体開催年度の2015年までとするのも一案だと思います。
④市民の参画
この仕組みづくりこそ、実は一等大事なことのひとつであると思っています。例えば、景観市民会議を設置して、毎年特定地点からのレビューを市民メンバーに評価してもらう。そして提案をしてもらう。
良き景観を守り、形成していくことは、地元自治体が如何に市民の景観意識を向上させる仕組みを作るか、の一点に懸かっています。そのための景観計画の策定だと思います。
そして、これを実現するのはやはり人材です。この計画は息の長い計画であるが、行政と住民等が一歩一歩より良き地域づくりを作っていくための強力なツールになって欲しいと願っています。
和歌山県景観ガイドライン
Posted by ecell at 23:38│Comments(0)
│行政